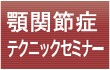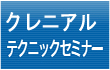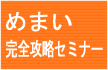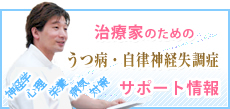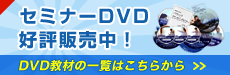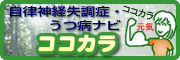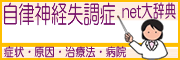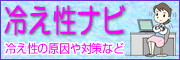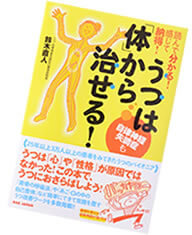2019年04月のメルマガ
2019年04月のメルマガ
顎と舌とめまいの関係 日本自律神経研究会 No.198
配信日:2019.04.30
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
ここ数回のメルマガで、顎関節症についてお伝えしておりますが、本日は『顎と舌とめまい』の関係をお伝えします。
前庭頚反射(ぜんていけいはんしゃ)という反射をご存知でしょうか。
体が傾いても重力に対して顔を真っすぐに保つ反射です。
実はこの前庭頚反射は、顔に対して「顎」と「舌」も反応するのです。
例えば、顔が右に傾くと(頸椎右側屈)顎は右側が上がるようになります。
簡単にいうと右の咀嚼筋(側頭筋・咬筋・内側翼突筋)が緊張するのです。
そのため、無意識に右側で噛む癖がつきます。
いわゆる「片噛み」になります。
首を右側屈したり左側屈したりしながら噛んでみて下さい。
倒した方の噛みしめが、強くできることを感じられます。
(このようにならない方は、顎がゆがんでいる可能性があります)
また、顔は真っすぐのまま顎の右側が上がると、舌は右側が下がります。
これにより、舌を下げる右側の舌骨舌筋という筋肉が緊張することになります。
つまり、顔・顎・舌は、お互いに補正するようにバランスを取っていくのです。
更に、顔が右に倒れているのにも関わらず、顎の右側が上がらないと、舌がそれを補正しようとします。
つまり、舌の右側が上がります。
この場合、右側の舌骨舌筋の筋トーヌスが低下するか、左側の舌骨舌筋が緊張し、左側の舌を下げることで相対的に右を上げるようにします。
これでもバランスが取れなくなると、前庭頚反射がうまく行えなくなります。
すると、顔を重力に対し真っすぐに保てなくなり、ふらつきが起こる場合があります。
顔が右に傾いたままですと、右側にふらついてしまうのです。
患者さんは、この状態を「めまいがする」と表現することがあります。
顔を真っすぐ保つための重要な要素の一つとして、「顎や舌が正常に動く」というものがあるのですね。
『顎関節』や『めまい』については、来月セミナーを行いますので、興味がありましたら、詳細ページをご覧ください↓
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人
特別ワークショップセミナー 1DAY 開催 日本自律神経研究会 No.197
配信日:2019.04.26
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
今年も『特別ワークショップセミナー』の時期が来ましたのでご案内させていただきます。
私たちは、体と心の専門家といわれています。
当会で勉強される方は、体や心の専門的な教育を受けています。
しかし、そんな専門家の我々にも、生きていると様々な問題が起こります。
これらの問題をクリアして人生を楽しいものにしていく人と、問題をクリアできずに、何度も同じ問題が起こり、人生が暗く希望のないものになっていく人がいます。
当たり前ですが、生きている人は全員が1回目の人生です。
つまり…
「誰しもが人生のビギナーである」
ということです。
40歳には40年の経験があると思いがちですが、40歳の経験は初めてです。
それを「人生経験は豊富だ」と思って問題にあたると、問題は大きくなることが多いです。
ビギナーが犯しがちな間違いは何か?
それは勘違いです。
あなたはご自分のことを勘違いしています。
その勘違いを明確化していくと「本当の自分」が現れてきます。
ワークを行っていると、本当の自分に出会い、「こんな自分がいたのか」とびっくりする方も多いです。
そして本当の自分が思っていること、感じていることは今あなたが思っていることや感じていることと、大きく異なることもあります。
大きく異なれば異なるほど、その人の人生では問題が大きくなり、ストレスも大きくなります。
今の自分と、体の中に隠れた「本当の自分」が同じ方向を向いていると、人生はとても楽しく充実したものになります。
ご興味のある方は、詳細と申込みのページをご覧ください。
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人
あごの痛みの見分け方 日本自律神経研究会 No.196
配信日:2019.04.23
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
顎関節症の症状といえば、痛みや顎関節の動きの悪さというのが多いですが、本日は「痛み」についてお話しいたします。
顎の痛みに限らず、問題には切り分けが必要です。
例えば…
- 何もしなくても痛いのか
- 顎を動かしたときに痛みが増すのか
- 噛んだ時に痛いのか
- 顎を誰かに動かされても痛いのか
このように切り分けていく必要があります。
分かりやすく言うと…
何もしなくても痛い+顎を動かしたときに痛みが増さないという場合は、骨・軟骨・靭帯などには痛みに直結する問題がないと判断できます。
(間接的な問題がある可能性は残ります)
骨が折れていたら動かせば痛い。
軟骨が削れていたら動かせば痛い。
靭帯に問題があれば動かせば痛い。
分かりやすくするために、ざっくりと単純にお伝えしますが、こういうことになります。
では上記の場合、どこが悪いのでしょうか?
何もしなくても痛い+顎を動かしたときに痛みが増さないという場合は、神経への酸素不足による「痛覚神経の過敏による痛み」の可能性が高いです。
神経は酸素が不足すると過敏になります。
それが痛覚神経で起これば痛みとなって現れます。
(過敏が弱ければシビレとなって現れます)
私の臨床上では、4割ぐらいの顎関節症はこの痛みです。
では、なぜ神経が酸素不足になるのでしょうか。
それは、前回お話しした食いしばりとも関係してきます。
食いしばるということは、咀嚼筋(側頭筋・咬筋・内側翼突筋)が緊張しているということです。
筋肉が緊張すると、血管が圧迫され血液の流れが悪くなり、酸素が届きにくくなり酸素不足が起こります。
また、前回のメルマガでお伝えしました通り、咀嚼筋の緊張が脳に伝わり脳が興奮します。
すると、自律神経の交感神経が働き、血管を収縮させてしまいます。
そうすると、酸素が届きにくくなり酸素不足が起こります。
つまり、関節を調整するより前に筋肉の緊張を取ったり、脳の興奮を抑えたりする施術が必要になります。
逆にいつもは痛くないけれど、ものを噛むときに痛むとします。
噛むという行為は、筋肉、靭帯、関節円盤、軟骨、下顎骨、上顎を使いますので、これらのどこが問題なのかを切り分ける必要があります。
例えば、顎を他人に動かしてもらった場合、筋肉は使いません。よって、顎を他人に動かしてもらって痛くない場合は、筋肉に何かの問題があると考えられます。
その他にも、顎を「猪木のまね」のようにしたときに痛みがあるかどうかのチェックをします。
この場合、軟骨や関節円盤に一番負担がかかりますので、痛みがあればそこを疑います。
本来はもっと細かく診ていくのですが、考え方としてはこのような感じになります。
これは顎に限ったことではないですが、症状に対して「何が問題なのか」というのをきちんと理解してから施術することが重要です。
適当にやっていたら改善しちゃった!という場合、なぜ改善したのかなどを追及していかないとなりません。
なぜなら、同じ顎関節症でも悪化させてしまう場合があるからです。
問題を明確にするのは、とても重要なのです。
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人
顎関節症。食いしばりの影響 日本自律神経研究会 No.195
配信日:2019.04.16
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
前回のメルマガでは三叉神経のお話をしましたが、今回は食いしばりについてお話しします。
顎関節症の方は、食いしばりがある方が非常に多いです。
食いしばる筋肉は、咀嚼筋と呼ばれます。
食べ物などを噛む筋肉であり、以下の3つの筋肉のことを指します。
・側頭筋
・咬筋
・内側翼突筋
これらの筋肉が無意識に緊張してしまい、食いしばりが起きます。
人によっては食いしばりながら歯ぎしりも行います。
咀嚼筋の力は非常に強く、食いしばりや歯ぎしりが続くと、顎に非常に大きな負担がかかり、顎関節症になります。
また、この咀嚼筋の緊張が強いと、その緊張は前回お伝えした三叉神経を通して小脳、そして大脳へと伝達され、脳が緊張状態になります。
脳が緊張状態になると自律神経が乱れてしまい、不眠・めまい・頭痛など、様々な症状が出るのです。
また、緊張状態は更に筋肉を緊張させるため、食いしばりや歯ぎしりが更にひどくなるという悪循環が始まります。
更に…
咀嚼筋の噛む力は篩骨に集まります。
そのため、食いしばりが続くことで篩骨に対して不必要な力が入り続けます。
篩骨の鶏冠という部分には大脳鎌が付着しているため、食いしばりの力は脳硬膜にも伝わります。
その結果、頭蓋骨にゆがみが起こることも少なくありません。
そのため、咀嚼筋である側頭筋・咬筋・内側翼突筋の緊張を取る必要があります。
これらの緊張が取れると、顎関節症が改善するとともに脳の緊張も取れ、様々な症状が改善していくのです。
このように顎関節症は全身に影響するため、施術できるようになると様々な症状に対応することができます。
セミナーでは、顎関節症が様々な症状にどのように関わっているか、また、どのように治していくかをお伝えします。
ご興味がある方は、開催日が近づいてきていますので、お早めにお申し込みください。
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人
顎関節テクニックの可能性は大きい! 日本自律神経研究会 No.194
配信日:2019.04.04
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
先週のメルマガで、入門セミナーでは、
「顎関節症テクニックの重要性を分かっていただき嬉しく思います」
と、お伝えしましたが、今日はそのことについてお話しします。
【顎関節症と三叉神経】
ここであなたに一つ質問です。
「脳幹」は、健康状態にどのくらい重要でしょうか?
分かりきったことですが、健康状態を通り越して、生きるうえで脳幹はとても重要な場所です。
そのため、脳幹の働きを正常にさせることが健康的に生きるために必要な条件になります。
この脳幹は、中脳・橋・延髄の3つに分けることができます。
そしてこの3つ全てに神経核を持っている神経があります。
それは「三叉神経」です。
そして、この三叉神経と顎関節はとても深く関連しています。
そのため、顎関節症をそのまま放置しておくと、脳幹全体の機能が低下してしまい様々な症状が出てしまうのですね。
では、詳しくお伝えしていきます。
【三社神経の概要】
三叉神経は、以下の4つの神経核を持っています。
三叉神経中脳路核(感覚神経・中脳)
三叉神経主知覚核(感覚神経・橋)
三叉神経脊髄路核(感覚神経・延髄)
三叉神経運動核 (運動神経・橋)
「三叉神経中脳路核」は、咀嚼筋の筋紡錘や腱紡錘からの情報が入るところです。
つまり、咀嚼筋の緊張度を感知しています。
ここが狂えば、咀嚼筋の緊張度がおかしくなってしまいます。
それは、下顎の位置がずれることを意味し、顎関節症に深く関係します。
「三叉神経主知覚核」は、顔面部の触圧覚の入力があります。
当然、顎周辺の触圧覚も感じています。
ここが狂ってくると、顎に違和感などを覚えることもあります。
「三叉神経脊髄路核」は、顔面部の温痛覚の入力があります。
ここが狂うと顎などに痛みを感じやすくなるのは容易に想像がつくでしょう。
「三叉神経運動覚」は、咀嚼筋の運動をコントロールしているところです。
ここが狂うと、顎がうまく動かせなくなります。
つまり、顎関節症は三叉神経の4つの神経全てに異常を起こすことが多いのです。
そして、この4つの神経に異常が起こるということは、それぞれの神経核がある、中脳・橋・延髄の機能が乱れ、自律神経系の働きがおかしくなり、頭痛・めまい・不眠・吐き気・など様々な不快な症状が現れるのです。
顎関節症が全身の症状に関係するということを生理学的にお伝えすると、このような形になります。
顎関節症を改善させれば、当然これら三叉神経の4つの神経は正常化し、中脳・橋・延髄の働きも正常化していくのです。
これは自律神経の機能が正常化するということなのです。
いかがでしたでしょうか。
少し解剖生理が入り、文字だけでは理解しづらいかもしれませんが、本コースでは、こういったことも解剖学図を見ながら原因から治し方まで丁寧に説明しますので、理解しやすいと好評をいただいています。
しかも、大事なところは何度も説明します。笑
そのため、顎関節症に対して自信をもって施術できるようになります。
興味がありましたら、ぜひご参加ください。
参加しておいて良かったと思えるセミナーになるでしょう。
詳しくは下記ページをご覧ください↓
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人
新しいセミナーの告知 日本自律神経研究会 No.193
配信日:2019.04.04
こんにちは、日本自律神経研究会事務局です。
事務局より、セミナー開催予定をお知らせいたします。
●特別ワークショップセミナー 1Day
東京:
2019年7月21日(日) 10:00~18:00
NATULUCK茅場町新館 2階大会議室
大阪:
2019年9月 1日(日) 10:00~18:00
新大阪丸ビル新館 711号室
※セミナーの詳細は決まり次第、こちらのメールマガジンにてご案内いたします。
その他セミナーの詳細は、こちらよりご確認ください。