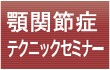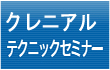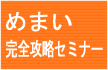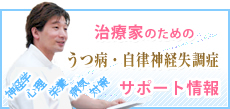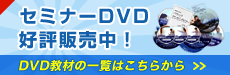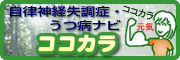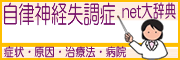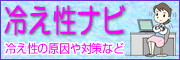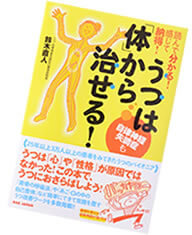2023年04月のメルマガ
2023年04月のメルマガ
前頭葉の活性化:大脳新皮質の知識 part3 日本自律神経研究会 No.238
配信日:2023.04.27
◆刺激のタイミング
◆何が何処にあるか?
◆まとめと予告
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
大脳新皮質(以下皮質)に関して2週連続で配信しましたが、いかがでしたでしょうか。
振り返りますと…
- 前頭葉はいちばん進化した皮質
それだけに疲労に弱い。
疲労すると、感情コントロール・予期・計画・実行する能力が低下。
すると、うつの症状が出現。 - 対策として…
刺激から遠ざかる・深呼吸をして酸素を取り入れる。
このようなことをお伝えしてきました。
では、3回目の今回は、「前頭葉の活性化」についてお話しします。
<< 刺激のタイミング >>
脳と神経の活性化には「酸素・栄養・刺激」が重要です。
逆にいうと、これらがなければ機能はどんどん低下します。
前回のメルマガで
- 刺激からできるだけ遠ざかる。
- 深呼吸をおこなう。
とお伝えしたのは、疲労しているからであって、疲労から回復したタイミングでは、刺激を与えることが重要となります。
刺激と休養(酸素と栄養の補給)の繰り返しで脳と神経は活性化していくのです。
<< 何が何処にあるか? >>
前頭葉は、単体では何も刺激を感じられません。
なぜなら、前頭葉は入力系の神経ではないからです。
前頭葉には、後頭葉・側頭葉・頭頂葉が感じた刺激が伝達されます。
つまり、前頭葉を刺激するには他の皮質を使うことが必要なのです。
これだけでは分かりにくいので、視覚を例にしてお伝えします。
目で捉えた視覚情報は、後頭葉と頭頂葉に伝達されます。
実は視覚野は目で捉えるだけで、
・それが何であるか、
・それが何処にあるのか、
までは分かりません。
見たものが「何か」が分るのは、視覚情報が側頭葉に伝達され、記憶の中から見たものと同じようなものを選択しているからです。
また、見たものが「何処」にあるのかは、視覚情報が頭頂葉に伝達され、見たものが空間内のどこに存在するのかを認識しているからです。
これは、自分の体性感覚情報を中心として感じています。
例えば目の前にバナナがあるとします。
側頭葉が働いていて、頭頂葉が働かなければ、見たものがバナナであることは分かりますが、どこにあるのか分からず手でつかむことができません。
逆に、側頭葉が働かず頭頂葉が働いていれば、見たものは何か分かりませんが、手でつかむことができます。
これら側頭葉と頭頂葉は、機能が正常であれば、それぞれ前頭葉にその情報を伝達します。
つまり…
見たものが何で何処にあるのかを前頭葉は知ることになり、その情報をもとにどのように行動をするのかを冷静に判断します。
例えば…
目の前に怒った顔の人がいれば逃げ出したいですが、それが自分の上司なら逃げるわけにいかないなと思い、逃げるという行動を抑制する決断を前頭葉は行います。
この例では、視覚情報をスタートにお話ししましたが、最終的には五感全てが前頭葉に伝達されます。
つまり、五感全てが前頭葉への刺激となります。
そのため、前頭葉の活性化には様々な感覚を感じることが重要となるのです。
聞いたことのない音楽、
行ったことない場所、
味わったことのない食べ物など
なじみのないものほど、前頭葉を活性化させることになります。
「そんなことか」と思う方もいるでしょうが、脳の機能を理解していると更に効果的な方法が簡単にできるようになります。
詳しくは次回お伝えいたします。
<< まとめ >>
前頭葉を活性化させるには刺激も重要。
刺激とは感覚であり、五感全てが前頭葉に伝達されるため、適度であれば活性化につながる。
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人
前頭葉の疲れの対策:大脳新皮質の知識 part2 日本自律神経研究会 No.237
配信日:2023.04.20
◆低刺激と酸素
◆深呼吸で症状が悪化しやすい人
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
先週お送りした皮質(大脳新皮質)の豆知識はいかがでしたでしょうか。
本日は、「前頭葉の機能が低下したときの対策」をテーマにお伝えします。
<< 低刺激と酸素が重要 >>
前回、「前頭葉はいちばん疲れに弱い」とお伝えしました。
分かりやすく、そして結論からいいますと、「疲れ」とは、刺激に対して酸素が足りないことを指します。
つまり、前頭葉の機能が低下したときの対策は、刺激を少なくして酸素を増やすことです。
つまり…
1.刺激からできるだけ遠ざかる。
2.深呼吸をおこなう。
ということになりますね。
ではこの2つをご説明いたします。
1.「刺激からできるだけ遠ざかる」
五感の感覚をできるだけ少なくすることです。
光・音・運動などの固有感覚・臭いなどもできるだけ少なくすることが重要です。
うつの方が引きこもったり昼夜逆転になったりしますが、これは、低刺激を維持するやり方なので症状が重症の場合はこれらを無理に治そうと思わない方がいいのです。
<< 深呼吸で悪化しやすい人 >>
2.「深呼吸をおこなう」
酸素は一番のエネルギー源になります。
ですから、酸素を供給しないと前頭葉は活性化しません。
そのため、「深呼吸」という当たり前のことがとても大事になります。
しかし、注意が必要になります。
とある研究機関が発表したデータによりますと、通常、深呼吸をすると副交感神経が活性化するのですが、逆に副交感神経の機能が低下してしまう人もいるということです。
それはどんな人かというと、呼吸筋が緊張している方です。
呼吸筋が緊張していると深呼吸をするのに大きな負荷がかかり、まるで筋トレをしているようになります。
つまり、深呼吸しても酸素がたくさん体の中に入らないばかりか、副交感神経の機能も低下してしまうのです。
このような方は、深呼吸をしても血液中の酸素濃度が下がってしまうことも多いです。
そのため、まずは呼吸筋をゆるめる手技を行う必要があります。
<< まとめと予告 >>
いかがでしたでしょうか。
当たり前と言えば当たり前ですが、疲れに弱い前頭葉をいかに回復させるは低刺激と酸素が大前提です。
それ以外は何をやっても意味がないどころか、症状を悪化させてしまうことになるのです。
では、低刺激と酸素の対策を十分にやった後にはどのようにアプローチしたらいいのでしょうか?
これは次回、皮質全体の解剖と生理の解説をしながらお話をさせていただきます。
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人
申し込みは確実にお願いします! 日本自律神経研究会 No.236
配信日:2023.04.10
こんにちは、日本自律神経研究会(JANA)の鈴木です。
会員の方にはFacebookでもお伝えしましたが、5月30日(火)・31日(水)に、レベルアップセミナー21を開催します。
テーマは大脳新皮質へのアプローチ。
複雑な大脳新皮質(以下皮質)の働きをわかりやすく説明するにはどうしたらいいか考えていましたが、大枠が決まりました。
伝えたいことがたくさんあり、既にテキストが70ページを超えてしまい、2日で終わるのか疑問になってきました(^^;)
◆内容予告として...
皮質の直接的な働きはこうです。
見たもの
感じたもの
聞いたものなどが何かを認識しながら、そのものがどこにあるのかを認識する。
その情報からどのような情動を起こすかを決め、どのように動くかを決め、体に運動指令を出す。
このような流れで働きますが、この流れのどこかに機能低下があれば、そちら側の皮質全体の機能が低下していきます。
皮質の機能の低下は、同側の脳幹の機能を低下させ、以下のことが起こります。
- 交感神経の抑制の低下。
- 痛覚抑制の低下。
- 筋緊張の抑制の低下。
- 姿勢制御の低下。
つまり…
右側の皮質に機能低下があれば、右側の交感神経が過剰に興奮し、右側の痛覚が過敏になり、
右側の筋緊張が亢進し、右側の姿勢が乱れてくる
と言うことです。
ちなみに姿勢の乱れは呼吸の乱れとなり、体が酸素不足になっていきます。
このようなことでいろいろな症状が出てくるのですが、今回はこれらに対してどのようにアプローチしていくかをお伝えします。
~追伸~
最近セミナーの参加申込みを忘れる方が多く、締め切りが終わってから「参加したいのですが…」とおっしゃる方が多いです。
参加そのものはとても嬉しいのですが、事務局が結構バタバタしますので、参加する予定の方は、忘れないよう早めにお申込みくださいね。
現在、おかげさまでクレニアルテクニックセミナーは満席。
大阪マスターコース、レベルアップセミナー21が申込み受付中です。
どちらも申込み締め切り日が迫っています。
お忘れのないようにお願いします。
●大阪マスターコース
(参加資格:プラクティショナーコースご卒業又は受講中で、会員の方)
●レベルアップセミナー21
(参加資格:日本自律神経研究会会員の方)
よろしくお願いします。
日本自律神経研究会 代表 鈴木直人